「今月の講義を聴いての感想」
参禅会 五十嵐嗣郎
今月の提唱
『正法眼藏』「禮拜得髄」の巻(1)
 修行阿耨多羅三藐三菩提の時節には、導師をうることもともかたし。その導師は、男女等の相にあらず、大丈夫なるべし、恁麼人なるべし。古今人にあらず、野狐精にして善知識ならん。これ得髄の面目なり、導利なるべし。不昧因果なり、儞我渠なるべし。
修行阿耨多羅三藐三菩提の時節には、導師をうることもともかたし。その導師は、男女等の相にあらず、大丈夫なるべし、恁麼人なるべし。古今人にあらず、野狐精にして善知識ならん。これ得髄の面目なり、導利なるべし。不昧因果なり、儞我渠なるべし。
すでに導師を相逢せんよりこのかたは、萬縁をなげすてて、寸陰をすごさず精進辨道すべし。有心にても修行し、無心にても修行し、半心にても修行すべし。しかあれば、頭燃をはらひ、翹足を學すべし。かくのごとくすれば、訕謗の魔黨にをかされず、断臂得髄の祖、さらに佗にあらず、脱落身心の師、すでに自なりき。
髄をうること、法をつたふること、必定して至誠により、信心によるなり。誠心ほかよりきたるあとなく、内よりいづる方なし。ただまさに法をおもくし、身をかろくするなり。世をのがれ、道をすみかとするなり。いささかも身をかへりみること法よりもおもきには、法つたはれず、道うることなし。その法をおもくする志氣、ひとつにあらず、佗の教訓をまたずといへども、しばらく一二を擧挙すべし。
今月の所感
昨年の11月で「身心学道」の巻のご提唱が終わりました。今月から「礼拝得髄」の巻のご提唱が始まりました。
この「礼拝得髄」の巻では、女性が沢山登場します。道元禅師の鎌倉時代は武士が中心の社会となり。男尊女卑の風潮が強まってきた時代です。しかし道元禅師は仏法の前では男女の別はないことを強調されています。この時代にそのような主張を展開するには、そうとうな決意がなければできなかったのではないかと思います。
 それでは最初の「修行阿耨多羅三藐三菩提の時節には、導師をうることもともかたし」。
それでは最初の「修行阿耨多羅三藐三菩提の時節には、導師をうることもともかたし」。
「阿耨多羅三藐三菩提」とは梵語の「アヌッタラサンミャクサンボディー」を、音そのままに漢字に直したものです。「アヌッタラ」は最上の、「サンミャク」は均衡のとれていること、「サン」は正しい、「ボディー」は覚りとか智慧ということです。だから「阿耨多羅三藐三菩提」とは、最高で均衡のとれた正しい教えということになります。
最高で均衡のとれた正しい教えというのもを「修行する」、実際に実践する、「時節には」、時には、「導師をうることもともかたし」、素晴らしい先生を得ることが大事であるけれども、それは最も難しいことである。
それではその先生とはどのような人かというと、「その導師は男女等の相にあらず、大丈夫なるべし、恁麼人なるべし」。
先生は男性であるとか女性であるとか、性別には関係なく、「大丈夫なるべし」。「大丈夫」というのは、一人前の人間ということ。だから立派な人間でなければならない。
「恁麼人なるべし」、「恁麼」とはそのような、このようなという、言葉では表現できない場合に使う言葉です。即ち、先生となるような人は、こういう人と一概に表現できないということです。
こういう人が先生だとレッテルと張ると、その言葉に縛られてしまいます。例えば「偉い人」といえば、偉いだけになってしまい、もっと他の要素が表現できなくなってしまいます。従って恁麼人とは、こうだああだと決めつけることのできない人ということになります。
「古今人にあらず」。
昔の人は偉くて、今の人はダメ、というようなことはない。逆に今の人は知識が豊富で、昔の人は知識が少ないからダメ、ということでもない。今とか昔とかの隔てをしてはいけない。
「野狐精にして善知識ならん」。
狐は化かすことができ、変化自在である。そのように本物の導師たる善知識は、狐のように変化自在な働き、臨機応変、適材適所の素晴らしい働きができなくてはダメである。沢山の知識を持っているだけではダメであるということです。
「これ得髄の面目なり、導利なるべし。不昧因果なり、儞我渠なるべし」。
この得髄は「礼拝得髄」の得髄です。達磨さんが四人の弟子に、自分の悟った内容を示すように言ったところ、二祖慧可は只、達磨の前に行って礼拝するのみであった。そうしたら達磨さんは「汝はわしの髄を得た」と言って、袈裟を譲って印可を証明されたという故事があります。これを取って「礼拝得髄」という巻が書かれたのです。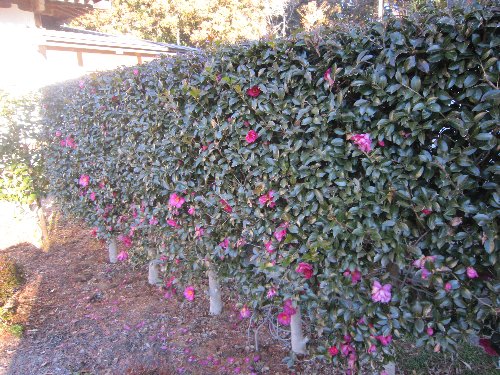 従って導師たる人は仏道の真実を得た人であり、「導利なるべし」、他の人を指導し、様々な利益を与えるような人であり、「不昧因果なり」、仏道の根本である因果の道理に明るい人であり、「儞我渠なるべし」、その得髄した人は、この提唱を聞いているあなた方自身であり、私自身であり、あの人でもある。
従って導師たる人は仏道の真実を得た人であり、「導利なるべし」、他の人を指導し、様々な利益を与えるような人であり、「不昧因果なり」、仏道の根本である因果の道理に明るい人であり、「儞我渠なるべし」、その得髄した人は、この提唱を聞いているあなた方自身であり、私自身であり、あの人でもある。
「すでに導師を相逢せんよりこのかたは、萬縁をなげすてて、寸陰をすごさず精進辨道すべし」。
一度本当にこの人が自分の先生だという方に出合ったら、さまざまの煩わしいことを一時に捨てて、時を惜しんで、精進辨道しなくてはならない。
「有心にても修行し、無心にても修行し、半心にても修行すべし」。
修行の仕方としては、意識的に修行する場合もあるし、無意識のうちに修行する場合もあるし、有心と無心とを兼ねた半心で修行する場合もある。どのような心掛けででも修行すればよい。要は修行の中味が大切なのですね。
「しかあれば、頭燃をはらひ、翹足を學すべし」。
頭燃を払う。頭の髪の毛に火が付いたら大変です。あわてて燃えている火を払いのける。そういう緊急の事態を迎えたと同じような気持ちで修行にあたりなさい。
翹足とは、かかとを上げてつま先立って歩くことです。お釈迦さんが過去世において弗沙佛が火定三昧に入っているのを見て、心中に歓喜の念を生じ、合掌して片足をつまんだまま、七日七夜を過ごしたという故事にもとづいています。
「かくのごとくすれば、訕謗の魔黨にをかされず」。
このように一所懸命に修行するならば、「訕謗」はそしる、仏道修行者を誹謗しようとする「魔黨にをかされず」、悪魔の連中に邪魔されることがない。
「断臂得髄の祖、さらに佗にあらず、脱落身心の師、すでに自なりき。」。
断臂得髄とは二祖慧可大師のことです。雪の嵩山少林寺で、臂を切って仏道の真実をを得たと伝えられる慧可大師はとは、他の人のことではないあなた方であり、自分自身ののことだと言われているのです。
「髄をうること、法をつたふること、必定して至誠により、信心によるなり」。
二祖慧可が達磨さんから髄を得、法が伝えられたことは、必ずただ偏に誠の至り、堅固な信心というものが根本にあり、それだけによって法が伝えられたということです。
「誠心ほかよりきたるあとなく、内よりいづる方なし」。
誠の心というものは外からやってくるものではない。また、自分の内側から湧き出てくるというものでもない。では何かというと、
「ただまさに法をおもくし、身をかろくするなり」。
これは凄いですね。この語句が今回の最も重い言葉です。 仏法を重くし、自分の身を軽くする。自分の身を捨てて、仏法の為にというものが心から出てくる。これが信心であり誠心です。
仏法を重くし、自分の身を軽くする。自分の身を捨てて、仏法の為にというものが心から出てくる。これが信心であり誠心です。
自分の身を捨てるとは、自分を無くしてしまうことではなく、自分をやめる、自分の欲をなくす、自我意識をやめることです。坐禅中の只管打坐です。
坐禅の時は己のちっぽけな自分をやめて、大自然の呼吸と一致するように、自然の息吹と一致するように坐る。そのような坐禅を長く続けて行けば、誠の心や信心というものが具わってくるのだと思います。
また、この句は『仏遺教経』にある「節身時食清浄自活(身を節し、時に食して、清浄自活せよ)」と同じ意味であると、明石方丈様は言われました。
「世をのがれ、道をすみかとするなり」。
俗世のさまざまな雑事に忙殺されるよりも、真実の道、仏道に早く親しんで、我が家としなければならない。
「いささかも身をかへりみること法よりもおもきには、法つたはれず、道うることなし」。
少しでも自分の身を大切にし、法よりも自分自身を重くしたならば、本当の仏法は伝わらない。
「その法をおもくする志氣、ひとつにあらず」。
法を重くする志とは、何かというと、それはひとつではない。
「佗の教訓をまたずといへども、しばらく一二を擧挙すべし」。
他人の教えを待つまでもないけれども、しばらく一つ二つの例を取り上げてみよう。
今月のお知らせ
令和7年の最初の定例参禅会です。今年の年番幹事は河本健治さんと齋藤正好さんのお二人です。幹事さんは何かと大変でしょうが、今年一年間宜しくお願いいたします。
境内はびっしりと霜が降りていましたが、昨年末から雨が少なく、白菜やキャベツなどの野菜が高騰しています。またインフルエンザなど風邪も流行しそうで、新年早々雲行きが怪しい風情です。
齋藤年番幹事からのお知らせ
・腰痛に悩まされていますが、脱力して年番幹事を続けられるように努めて参りたいと思います。
・涅槃会の参加予定者は10名です。配役の人は13時までに集合してください。法要の開始は14時です。
河本年番幹事からのお知らせ
・齋藤さんと一緒に参禅会のスムーズな運営に努めた行きたいと思います。
杉浦『明珠』編集委員長からのお知らせ
・『明珠』83号の原稿が予定通り集まりました。
・小畑元代表は五香にある施設に入っています。1月16日に面会してきましたが、自力での歩行は難しくなってきました。
明石方丈様からのお知らせ
・この頃は寒暖の差が激しくなってきました。体調に気を付けてください。
・東葛地区百年の本の横に、椎名老師の『沼南之宗教文化史』が並んでいました。
今月の司会者 齋藤正好
今月の参加者 14名
来月の司会者 齋藤正好
 印刷
印刷